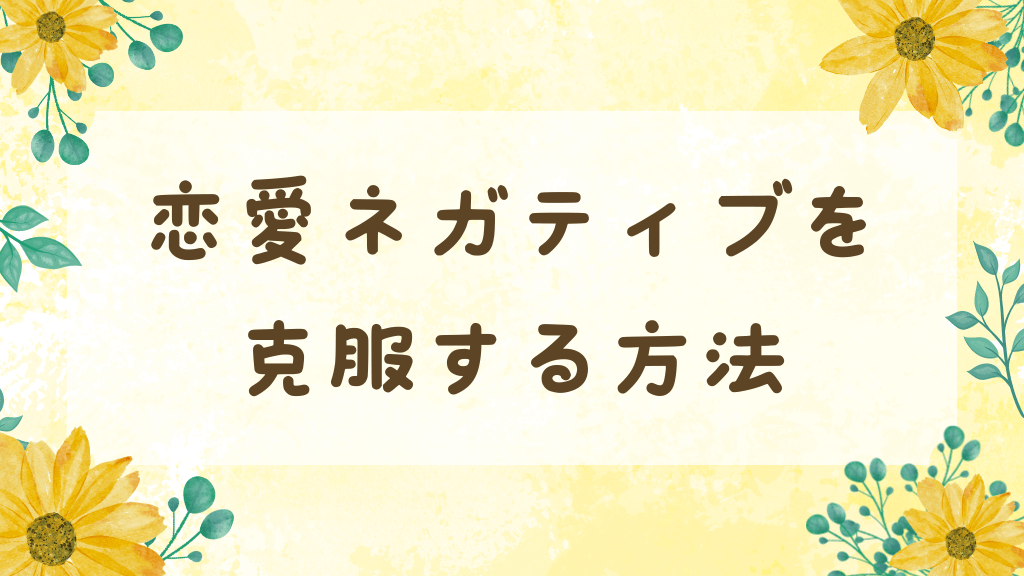第3話 わずかな希望
神様、お願いだから、この嫌な予感があたりませんように、、
心の中で強く願って、ゆっくりと目を開けた。
彼が指をさす先には、HOTEL ラグジュアリーパラダイスと書かれたキラキラと輝くホテルだった。

ホテルというか、誰がどうみても典型的なラブホテルだった。
あぁ…神様なんかこの世にいない…
無神論者のくせに、
人のことも自分のことさえも信じないくせに、
調子のいい時だけ、神様にお願いごとしても叶うわけないか…
やはり予想通りだった。
眩しいくらいにネオンで光り輝いているラブホテルをただ黙って見ていた。
彼は、アプリでスワイプしまくって、疲れた私の指を止めた52人目の人だった。
すぐに会わずに大事な関係にしたくて、今日会うまでに1ヵ月という時間をかけた。
「お仕事お疲れ様でした。今日の夕食のメニューは?」
「風邪が流行っているから、気をつけてね」
「あー早く会いたいなぁ」
たわいもないアプリの会話が仕事で疲れた私を癒してくれていた。
何の楽しみもない生活の中で、ようやく見つけた希望だった。
希望の数だけ失望に変わるから、人生には何の期待もしないと言っていた友達のいう通りだった。
都会の雑踏とストレスの中で育った私にとって、
山に囲まれた環境で育った人は、素朴で純粋だと勝手に決めつけていた。
山形出身でお米が好きで、
川が好きな純粋な田舎少年をアピールし、
東京に状況して半年、真剣な恋愛がしたいと純粋ぶった会話をしていたのに、
やっぱり、コイツもクズだった。
初めての出会いの日にレストランの予約はしない、
50分間散々歩かされたあげく、何が食べたい?と聞いて夕食の店を二人で探そうとする会話もせず、
相手を疲れさせて休憩ラブホを狙うクズ男だった。
信号が赤から青に変わる。
純粋色白坊主君が夜空を見上げながら歩き出す。
私は、勢いよく、まわれ右で、駅に向かって歩き出した。
握りこぶしの手にどんどん力が入って震えている。
こぶしの中の爪が突き刺さって痛みが増してくる。
歩けば歩くほど、力が強くなり、爪が手にどんどん突き刺さっていく。
手が痛いはずなのに、その痛みは少しずつ上へ上と押しあげていく、
胸が痛い、心が痛い、息が荒くなる。
顔をしかめながら、絶対涙なんか流さないと強がるほど、
虚しさと悔しさが溢れて、涙が込み上げてくる。
相手にムカついているのではない。
またこんな男にひっかかってしまった自分に、
またこんな男に期待してしまった自分に嫌気がさしている。
少しでもこれが運命かもと信じてしまった自分が情けなくて、涙が止まらない。
土曜日の渋谷、
楽しそうにはしゃぐ人たちの中を下を向いて歩く。
みんなの横には誰かがいるのに、なんで私の横には誰もいないのだろう。
ただずっと、じっと下を向いて、アスファルトを見つめ、涙を拭いながら足早に駅に向かう。
人混みの多い渋谷が大っ嫌いだったのに、
週末の渋谷の人混みが自分の虚しさをかき消してくれているように感じて心地がよかった。